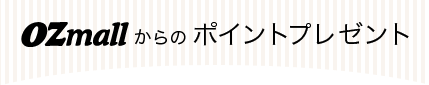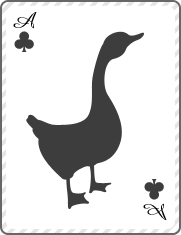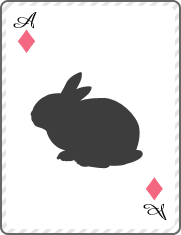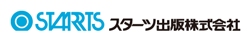【栄養士監修】献立の立て方完全ガイド!簡単で栄養バランスのよいメニューも紹介

新生活や同棲、結婚などを機に料理を作る機会が増え、栄養バランスが取れて手間なく作れる献立の立て方を知りたくなる人も多いのでは。この記事では、管理栄養士のアドバイスを交えながら、忙しくてもさっと作れる簡単な献立の例や、1週間分のメニュー例を紹介。献立づくりに役立つ情報をぜひチェックして。
更新日:2025/03/27
※アフィリエイト広告を含むPR記事です
今回お話を聞いたのは・・・管理栄養士の金丸利恵さん

「今、口にしたものがあなたの未来を作る」
毎日の食は心身の土台を整えはぐくむ重要な礎となります。管理栄養士の知識・経験に分子栄養学を取り入れ、レシピ開発、オンライン料理教室、栄養セミナー、ダイエットカウンセリングなどを行っています。
栄養的視点をもとに作った、無理なく続けられる、簡単で美味しいレシピに定評があり、幸せな未来をつくる「おうちごはん」をサポートしています。
1.献立の立て方は「主食・主菜・副菜」の組み合わせが基本

献立作りで最も重要なのは、「主食・主菜・副菜」の基本的な組み合わせ。これを意識するだけで、栄養バランスのとれた食事を実現しやすくなる。
主食:ご飯、パン、麺類
主菜:肉、魚、卵、大豆製品などのメインになるおかず
副菜:野菜、海藻、きのこを使用した小鉢など
献立を考える順番も重要。まず主食を決め、次に主菜を選び、それらに合う副菜をプラスするという流れで考えよう。メニューによっては汁ものなどを足すのも。
2.栄養バランスを意識した基本的な献立の立て方
主食・主菜・副菜を意識しても、栄養バランスが偏ってしまうこともある。ここでは栄養バランスを意識しながら献立を立てる基本的な考え方を解説。
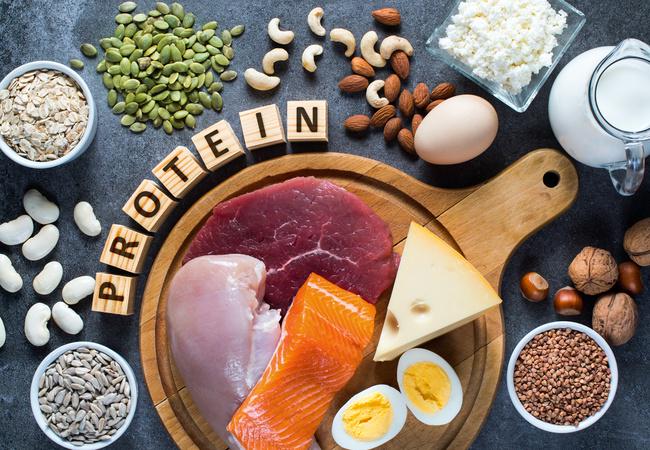
糖質、たんぱく質の確保
エネルギー源になる糖質と、体の土台となるたんぱく質の確保を意識することが大切。栄養バランスが整うだけでなく、自然と「主食→主菜→副菜」の流れで献立を立てることができる。
ただし、取り入れた糖質やたんぱく質をうまく使うためには補酵素としてビタミンやミネラルを摂ることも必要。特に30代以降は、エネルギーをうまく使えなくなると肥満につながる可能性が高まる。また、たんぱく質の摂りすぎは腎臓に負担がかかる場合などもあるので、適量を守ることを意識して。

色彩を意識する
野菜は色によって栄養素が変わるので、彩りを意識するだけで栄養バランスがとりやすくなる。カラフルな食事は、食欲がわきやすいというメリットも。1食の中で、下記のような色(野菜)を取り入れることを意識してみよう。
緑:ホウレン草、ブロッコリー、レタスなど
赤・オレンジ:ニンジン、トマト、パプリカなど
白:大根、カリフラワーなど
黄:カボチャ、コーンなど
すべてを取り入れるのが大変な場合は、緑・黄・赤の緑黄色野菜から優先して取るのがおすすめ。緑黄色野菜にはカロテンやビタミンC、ビタミンK、葉酸、ミネラルなどが豊富に含まれている。
3.1週間の献立を立てるときのポイント
献立は、1週間単位で考えるのがおすすめ。1週間分の献立を立てる際は、下記のポイントを意識してみて。

1週間分の主菜に使うたんぱく質材料を決める
まず、1週間分の主菜に使うたんぱく質の材料を決めるのがおすすめ(例/月:鶏肉、火:鮭、水:豚肉、木:サバ、金:牛肉など)。
食材のみだとイメージがわきにくい場合は、献立名でもOK(月:鶏の照り焼き、火:鮭のホイル焼き、水:回鍋肉、木:サバの味噌煮、金:牛肉とピーマンの炒め物など)。この場合、なるべくメイン食材が重ならないように意識して。
また、食材はローテーションすることでアレルギー防止にもつながる。肉→魚→肉→魚と日ごとに変えられると理想的。

副菜には野菜、海藻、きのこ類を使う
副菜には、野菜や海藻、きのこ類を使ったものがおすすめ。例えば青菜のお浸し、キュウリのもずく和え、きのこのマリネなどが選択肢になる。
なお、主菜・副菜ともに、食材の用意が間に合わないときや献立が思いつかないときは、ミールキットなどを活用するのもおすすめ。献立を考えたり材料を買ったりする時間や、下準備にかかる手間を減らせる。
ピックアップアイテム[PR]
パルシステム生活協同組合連合会
パルシステム
献立に悩む人の強い味方。ミールキットなら「パルシステム」
献立を考える時間がなかったり、食材の用意が間に合わなかったりしたときには、「パルシステム」のミールキットがおすすめ。カット済みの野菜で短時間で調理できるミールキットを豊富に用意。
管理栄養士監修商品もあり、健康を意識する人にもぴったり。週に1回、重たい食料品や日用品を玄関前まで届けてくれるので、買い物の手間を減らせる。
4.献立作り・食事の用意を効率よくするためのコツ
面倒に感じたり、時間がかかったりする献立作りや食事の用意を、少しでも楽に済ませたいと思う人は多いはず。管理栄養士に聞いた、効率のよい献立作りや食事の用意をするためのコツを知っておこう。

たまに市販品を活用する
すべてを調理しようと頑張りすぎず、市販品もうまく活用しよう。レトルトのカレーや、ミートソースは、野菜や肉などを炒めたり煮たりしてプラスすると味や栄養のバランスがとりやすくなる。
例えばチルドや冷凍のギョーザに野菜を足してスープ餃子にしたり、味付きの肉に野菜を足して肉野菜炒めにしたりと、アレンジ次第でさまざまなメニューを楽しめる。
また、冷凍野菜を活用するのも手。ビタミン、ミネラルが減少しているものはあるものの、量をとることでカバーしやすくなる。

野菜を事前にカットしておく
水菜やニラなど、切り方が決まっている野菜は購入後にカットしておくのがおすすめ。タッパーや袋に入れて保存しておけば、炒めものや味噌汁にさっと入れることができ、なにかと重宝する。
白菜、キャベツなどの葉物はザクザク刻んで袋に入れ、塩を少々振ってから保存を。水分が抜けてしんなりするので、そのまま食べてもおいしいのはもちろんのこと、炒めものや汁ものに入れると旨味が増す。

肉や魚に下味をつけて冷凍しておく
肉や魚は、下味をつけて冷凍しておくと便利。合わせだれを揉みこんだり照り焼きのたれをつけたり、魚には西京味噌を塗るのも。
下味をつけて冷凍保存しておいたものは、使う日の朝に冷蔵庫に移動すればOK。帰宅後はフライパンで炒めたり、トースターで焼いたりするだけで一品が完成する。ただし、冷凍した食材はなるべく早めに使い切ることが望ましい。

1週間の献立には“隙間”を作る
献立を1週間きっちり決めるのではなく、あえて献立を決めない“隙間”を作ることも大切なポイント。献立を決めない日の朝ごはんや副菜で、余った食材を使いきる意識を持つとうまくいく。
5.【栄養士監修】1週間分のおすすめ献立例
献立の立て方で悩んでいる人のために、管理栄養士が1週間分の献立の例を考案。普段の献立作りに役立ててみて。

月曜日の献立例
・主食:雑穀入りごはん
・主菜:ヒレカツ卵とじ
・副菜:ホウレン草とシメジのゴマ和え
月曜日は忙しい家庭が多いので、冷凍や総菜のヒレカツを使用。ロースカツに比べて脂身が少ないのがメリット。

火曜日の献立例
・主食:雑穀入りごはん
・主菜:鮭と野菜の包み蒸しレモン風味
・副菜:チキンサラダ(蒸し鶏、レタス、ワカメ、トマト、ドレッシング)
時短したいなら、蒸し鶏はサラダチキン、レタスはカット済みのものでもOK。

水曜日の献立例
・主食:ビビンバ
・主菜:(牛焼肉、もやし、ホウレン草、ニンジンのナムル、海苔、キムチ、温泉卵)
・副菜:ワカメスープ
ひとつの丼でさまざまな食材を味わえるので、汁ものを足すだけでOK。ナムルを作るのが大変なら、市販品を購入しても。

木曜日の献立例
・主食:雑穀入りごはん
・主菜:サバの味噌煮
・副菜:キュウリとワカメの酢の物
サバの味噌煮は、レトルトを活用するのも手。その場合、鍋に開けてきのこ類やネギを一緒に煮ると、具材を増やせる。

金曜日の献立例
・主食:具材ごろごろミートソーススパゲティ
・主菜:オープンオムレツ
・副菜:大根サラダ
スパゲティは、市販のミートソースに炒めたナスやきのこ、電子レンジで加熱したブロッコリーをプラスして野菜量をアップ。

土曜日の献立例
・主食:手巻き寿司(刺身盛り、厚焼き玉子、キュウリ、海苔、たくわん、カニカマ)
・主菜:冷奴
・副菜:具材いろいろ味噌汁
すし酢で混ぜたら具材を並べるだけで、調理の手間は省きつつイベント感のある献立に。味噌汁には余った野菜を入れれば、週末に食材を一掃できて一石二鳥。

日曜日の献立例
・主食:雑穀入りごはん
・主菜:ササミの味噌マヨコーン焼き
・副菜:ひじきの煮物
ササミを開いて、味噌マヨ+コーン+チーズを乗せてトースターで焼くだけと簡単。付け合わせにはレタスやキャベツがおすすめ。ひじきの煮物は、多く煮て冷凍しておくと翌週の副菜に。
6. 献立に迷ったら“包み蒸し”が便利

献立が思いつかないときのおすすめメニューは、“包み蒸し”。クッキングシートに肉や魚や野菜を入れて塩、コショウで味付けして包み、フライパンに水少々を入れて蓋をして蒸すか、電子レンジで5~7分加熱するだけ。朝に包んで冷蔵庫で保存しておき、帰宅後に加熱するという時短テクニックも使える。
メインの食材は鮭、タラ、サワラなどの魚、ひき肉、鶏肉などの肉のほか、魚介類もおすすめ。野菜はキャベツ、もやし、ブロッコリーやカリフラワー、トマト、ピーマンなどなんでも合い、きのこ類などを足すのもバランスがよい。
基本的には油を使わずに作れるので、レモン汁やポン酢で食べればよりヘルシー。さらに、味噌+みりん+バターでちゃんちゃん焼き風、オリーブ油+ニンニク+ハーブでイタリアン、とろけるチーズでチーズ焼き、マヨネーズ焼きなど、アレンジの幅が多く料理のレバートリーも増える。
ピックアップアイテム[PR]
パルシステム生活協同組合連合会
パルシステム
献立に悩む人の強い味方。ミールキットなら「パルシステム」
献立を考える時間がなかったり、食材の用意が間に合わなかったりしたときには、「パルシステム」のミールキットがおすすめ。カット済みの野菜がセットされた短時間で調理できるミールキットが豊富に用意されている。
管理栄養士監修商品もあり、健康を意識する人にもぴったり。週に1回、重たい食料品や日用品を玄関前まで届けてくれるので、買い物の手間を減らせる。
7.こんなときどうする?献立の立て方にまつわるQ&A
献立の立て方にまつわる、よくある疑問に回答していく。
Q.どうしても同じメニューや味付けになってしまい、マンネリしがち
A.マンネリを防止するためのテクニックとして、味付けのレパートリーや調理法ごとの献立をいくつか頭に入れておくことをおすすめします。
・レパートリー:しょうゆ味、味噌味、トマト、ホワイトソース、デミソース、オイスター、韓国風など
・調理法ごとの献立:焼き/照り焼き、塩焼き、ハンバーグなど、炒め/野菜炒め、肉炒め、魚介炒め、煮る/おでん、筑前煮、肉じゃが、蒸し/レンジ蒸しなど
「○○の素」「○○のタレ」といった市販の調味料の裏に書いてある成分表示をチェックして、材料の組み合せを真似てみるのも手です。
また、その都度レシピを見ながら調理をするのは手間に感じるもの。頭の中に材料や工程が浮かべばそのまま調理できるので、普段からレシピ本やレシピ動画をさりげなくチェックし、引き出しを作っておくとよいでしょう。
Q.家族の反応や感想を想像すると、献立作りの荷が重い・・・
A.料理は毎日のことですから、100点をめざさないことも大切です。調理する側にマンネリさやワンパターン感があっても、食べる方は意外と安心感を覚えていることも少なくありません。相手から指摘されない限りは、そこまで心配しすぎなくて大丈夫です。
また、「嫌だな」「面倒だな」と思いながらバランスのよい献立作りや調理を頑張るよりも、テイクアウト品を楽しく食べた方が家族みんなが機嫌よくいられることもあります。楽にも大変にも振り切らず、適度に自分のペースで料理しましょう。
Q.食材を無駄にしないコツは?
A.人数が少ない場合は食材を使いきれないことがあるので、割高でも少量を買ったほうがいいことも。状況に合わせて、まとめ買いをしないことも大切です。
また、冷蔵庫を定期的に掃除すれば、必然的に在庫をチェックできて一石二鳥。余った食材は、味噌汁に入れたり鍋にしたりして消費する日を作ると、在庫を減らせます。調理済みの料理を翌日食べない場合は、速やかに冷凍しましょう。
Q.野菜不足など、栄養バランスの偏りが気になる・・・
A.前述の通り、主食・主菜・副菜を揃えれば栄養バランスが偏りにくくなります。基本をあらためて見直してみましょう。
そのうえで、日本人の食事で不足しがちな栄養素は鉄とカルシウムと言われています。ひじき、切り干し大根、高野豆腐、干しシイタケ、ワカメなどの乾物や、あさりやかきなどの貝類、レバー、青い葉の野菜(小松菜、大根葉など)、ごま、だいず、小魚など、「まごわやさしい」を意識した献立を考えるとよいでしょう。
ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な緑黄色野菜も、積極的に摂りたい食材のひとつ。小松菜、ホウレン草、ブロッコリー、ニンジン、パプリカ、カボチャなど、色の濃い野菜を意識して取り入れることをおすすめします。
Q.食費を節約するコツはある?
A.鶏ムネ、豚小間、豆腐、おから、もやしなど、安価で栄養ある食材を使うレパートリーを増やしてみましょう。また、出盛りのものは安くて栄養が豊富なため、旬の野菜を買うことも節約につながります。
ただし、冷蔵庫の中は食材がいっぱいに入っている状態を避けたほうがよいので、安いからと言って大量に買いすぎないように注意しましょう。
一度に多めに作り、冷凍できるものは冷凍しておくと、手間と光熱費の節約に。例えばひじき煮や切り干し大根などの乾物は、冷凍に向いています。そもそも食材を無駄にしないことも大切なので、前述の「食材を無駄にしないコツ」も参考にしてみてください。
8.まとめ

なにかと大変な献立作りだが、まずは基本となる主食・主菜・副菜の組み合わせを意識すればOK。食材選びや調理法を工夫すれば、無理なくバランスのよい食事を楽しめる。
難しく考えすぎないことも大切なので、ときにはミールキットなどの市販品に頼ることも視野に入れてみて。自分や家族がご機嫌でいられる調理法や献立、味付けを模索しながら、毎日楽しく健康的な食卓をめざそう。