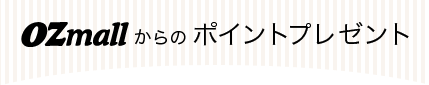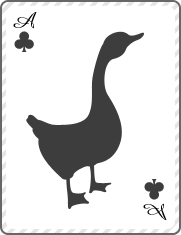「雑」と名前につくけれども雑には育てられぬ、手間ひまのかかる穀物、それが雑穀です。「雑穀王国」と名高い岩手県で、地域の食文化を守ろうと奮闘する若き担い手と、県が長年かけて開発した注目の雑穀の新品種に会いに金色〈こんじき〉のあわ畑を訪ねました。

農家の意地がつなぐ雑穀という歴史と文化
雑穀のことを深く学ぶために訪れたのは、国内の雑穀生産量の約6割を占める岩手県でも、特に栽培が盛んな県北(けんぽく)地域の二戸(にのへ)市。見事に穂を実らせたアワ畑でお話を伺ったのは、代々続く農家を継ぐため2007年に東京から戻った上野剛司(うわのつよし)さん。
「このアワは色味と食味がよくなった新品種の『いわてあわこがね』。モチアワと呼ばれるモチ種(粘りのないウルチ種もある)だから、白米に一割くらい混ぜて炊くとごはんがもちっとします。生産者目線で言えば、病気に強くて多収。背が低いから倒伏しにくく、コンバインで刈り取りしやすいのもありがたいですね」

県北で雑穀の栽培が伝統的に行われてきたのは、やっぱり冷害が多かったからだと思う、と上野さん。
「米がまったく育たないような寒い年でも、雑穀ならなんぼかは採れる。当時の凶作というのは今の比じゃないくらい生きるか死ぬかの問題だったから、貴重な救荒食物として重宝されていた。でもやっぱりみんな米が食べたいんですよ。だから父親の世代だと、弁当でヒエ飯を持ってきた人はフタで隠しながら急いで食べたそうです」

稲の品種改良や農作業の機械化が進み、岩手でも安定的に米が収穫できるようになると、雑穀を育てる農家は減っていきました。その理由は単に米の生産量が増え、雑穀の需要が減ったからではないようです。
「私は水稲を主力にしながら、アワ、キビ、ヒエ、タカキビといった雑穀を育てています。雑穀というくらいだから育てやすいイメージがあるかもしれませんが、実は水稲よりもずっと大変。生産量が限られているから農薬の開発も進んでいないので、使える除草剤が少ない。そうなると手作業で草を抜くしかない。だから誰もやりたがらないですよね。雑穀王国と呼ばれる岩手でも、育てている農家は絶滅危惧種かもしれません」

それでも上野さんは、効率的な輪作の方法を研究したり、機械化できる作業を増やしたりと、毎年毎年試行錯誤をしながら次世代へとつなげるために雑穀栽培の種をはぐくみ続けています。
「今はキロ単価で言えば米よりも高いです。でも面積あたりの収量は米の3分の1とか4分の1。手を抜いたらもっと下がります。それなのにずっと手間がかかる。それでも私が雑穀を育てているのは、ちょっとした使命感なんです。二戸の食文化として残したいという思い。最近までタカキビの栽培がほとんど途絶えていたから、郷土料理の『へっちょこ団子(※)』が昔はタカキビの粉でつくられていたというのを知りませんでした。それって寂しいじゃないですか」
※タカキビなどの雑穀の粉を熱湯で練って丸めて中央をへこませたもの。甘い小豆汁で煮て食べる。名前の由来は農作業で「へっちょ(苦労)」したことをねぎらう意味とも、へこんだ部分が「へそ」に似ているからとも

そんな上野さんの熱い想いに触れて、上野さんがここまで雑穀にこだわる訳がわかる気がしました。
「やればやるほど難しいですが、昔ながらのやり方を大切にしつつ、今風に変えられるところは変えて効率化する。仕事として成立するようにしないと自分も続かないし、続いてくれる人もいないでしょう。雑穀の魅力に足を突っ込んじゃったから、もう後戻りはできません。あとは二戸の農家としての意地とプライドしかないですよ。でも周りの人からは『あいつまだ雑穀やっているのか、ばかっこだなぁ』なんて思われているんでしょうね(笑)」

【取材ノート】
山間の地で上野さんが育てている「いわてあわこがね」の畑

【取材ノート】
収穫を控えたタカキビの穂。タカキビは郷土料理の「へっちょこ団子」に使われる

【取材ノート】
上野剛司さんの育てるヒエ畑で。取材は赤とんぼが飛び回る9月半ば。間もなく収穫時期

【取材ノート】
上野さんのヒエ畑にあった「ひえしま」。近所のおじいさんが「昔ながらのヒエの乾燥方法」として作ってみせてくれたものだそう。かつては脱穀したあとのヒエの茎や葉を乾燥させて家畜の飼料に用いられていた。
PHOTO/ATUSHI YOSHIHAMA