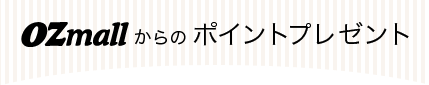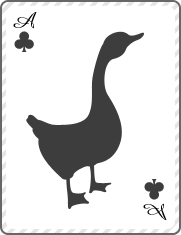紀州徳川家の城下町。6つの商店街からなる「ぶらくり丁」は、軒先に商品をぶらくって(ぶら下げて)売ったのが由来だとか。かつて繁栄を遂げたこの街に、今再び、Uターン組によるカルチャー・ムーブメントが起きている。
INDEPENDENT MOVIE THEATER/シネマ203

赤い階段を上った2階
そこは、街の外への出口
1970年代までの「ぶらくり丁」は、渋谷のスクランブル交差点並みに人が往来する一大商店街。そして劇場が5館以上も建ち並ぶ、映画の街でもあった。それらが1館残らず消えて久しいこの街に、2023年10月、ぽっかり点った小さな灯りがある。

「シネマ203」。ミニシアターよりさらにマイクロな、15席の映画館だ。北ぶらくり丁を折れると、古い建物の入口に、ギヨーム・ブラック監督『リンダとイリナ』のポスターが1枚。かろうじてこれを頼りに、狭い通路を奥へと進み、真っ赤な鉄の階段を上がる。203号室。ああ建物はアパートだったのだ、とハッとする、このざわざわするようなアプローチがすでに映画だ。

まさに“部屋”の規模だけど、本当に映画館になるの?と思いきや、いざ始まると、どんどん「映画と私だけ」の感覚に倒錯していくのである。なんだろう、この没入感は。遠くで響く放課後のざわめきといった些細な音まで、まるでその場にいるように聞こえてくるのだ。四角錐のスピーカーは、館主の高水美佐さん曰く「地元のオーディオマニア」による製作。椅子は、グッドデザイン賞を受賞したニーチェアエックスだ。折り畳み式だが、布がハンモックのようにすっぽりと身体を包み込み、危うく眠りそうになるほどの浮遊感。スクリーンを見上げる背もたれの角度も完璧で、映画のプロが「自分ならこれで観たい」ものを選んだんだな、とわかる。

高水さんはアメリカで映画を学び、東京の配給会社で買い付けから宣伝まで修業してきた人だ。フランス映画社。ビクトル・エリセやジム・ジャームッシュなどの作品を日本に伝えた、1980年代ミニシアターブームの立役者となった会社である。映画業界の最前線で目を肥やした彼女のプログラムは、だから全面的に信頼できるし、目が離せない。先の『リンダとイリナ』も、日本では東京「ユーロスペース」と和歌山「シネマ203」の2館だけで初公開、というミラクルだ。

「街と映画へ、恩返しをしたい」地元で育った高水さんは、父に連れられて行ったぶらくり丁で『キングコング』を観た日から、映画に夢中になった。学生時代、苦しいときは映画によって救われてきた。「現実はいろいろと厳しくても、映画館は2時間、街の外に出られる出口。だから映画を観た後、その人の人生が少しだけ楽しくなるような作品を選びたい」逃げ込める場所だから、表通りの1階じゃなくていい。密かに通えるアパートの一室、「その鍵をみなさんから預かっている」と彼女は言った。
シネマ203
TEL.090-8172-7074
住所/和歌山県和歌山市中ノ店北ノ丁22 北ぶらくり丁会館203 号室
※上映スケジュール、予約はHP・電話・メール・SNS メッセージより。スクリーン約180×270cm / 15 席/一般1700 円、大学・専門学校生1500 円、小中高校生1000円。リピーター割引あり
INDEPENDENT BOOK STORE/本町文化堂

本から得た好奇心を
イベントでさらに広げる
「シネマ203」から、北ぶらくり丁のアーケードを抜けて徒歩3分。この至近距離に、高水さんが「私より映画に詳しい」と舌を巻く嶋田詔太さんと、三木早也佳さんによる書店「本町文化堂」がある。近所で7年間「本屋プラグ」として営んできたが、今年3月に本町へ移転。洋裁学校だった建物の1階が本屋に、2階はイベントスペースになった。嶋田さんはここで、定期的に無声映画を上映しているのだ。

「楽士ってご存知ですか? トーキー以前の音のない映画には、専門の音楽家がピアノなどの楽器を生演奏して、映画に音楽をつけていました。それを再現するんです」
このイベントに合わせ、「シネマ203」で戦前の無声映画を特集上映したり、逆に映画のトークイベントを「本町文化堂」の2階で行ったり。

ほかにも僧侶や学者、作家に落語家、銭湯の跡継ぎなどユニークな専門家と手を組みながら、「点でなく、面で」和歌山のカルチャーをおもしろくしていく、まさに「文化堂」。ピアノもスクリーンもある。さらには音響設備、録音・DJブース、バーカウンターまで備えているから、あらゆるイベントが可能だ。「高校生のとき、雑誌で知るアート系映画やバンド、落語も、和歌山では身近になかったので。そういった原体験が、地元でできたらいいなと」

2階の話が長くなったが、そもそもの入口は、本だ。彼らにとってイベントは、あらゆる本を読んで得られた好奇心や興味を、さらに深掘りし、拡張し、共有する手段。実は嶋田さん、貪欲なまでの知りたがりなのである。それも「ラーメン文化の中の家父長制」とか「電気風呂鑑定士」とか「モンゴルのヒップホップ」とか。世の中に日々放出される書物の大河から、多くの人が見過ごしてしまうようなトピックスが、彼のアンテナには引っかかる。そうして一度気になってしまったら、「なんで? どうして?」 と追いかけずにはいられない性分らしい。

アジアに強い三木さんも含め、そんな知のハンターたちが探し出した本が、1階には集積されている。「今週発売の『少年ジャンプ』から、100年前の郷土史まで」本棚自体を、読み解いていくような感覚になる本棚だ。例えば食のあたりには、日々のレシピ本の棚があり、昭和の飲食店、民族の料理へと移り、やがて難民や移民の話につながっていくような。ゆるやかに、あるいは強烈にかかわり合う構造は、世界と同じだ。「本町文化堂」の表現はポップだけれど、ときに毒をもって、私たちの眠れる好奇心を揺り起こす。
PHOTO/MASAHIRO SHIMAZAKI WRITING/NAOKO IKAWA
※メトロミニッツ2024年8月号より転載