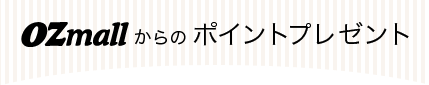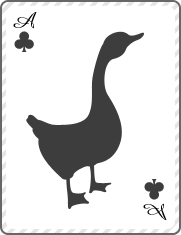モノづくりの過程に宿る 可視化することのできないものに
意識的でいられるかどうか
長野県松本市、静かな川のほとりの
印刷所を訪ねる旅で出会った奇跡
18年間一緒に暮らした猫が病気で亡くなったのは4月のよく晴れた日でした。その前に自分自身が体調を崩したこともあり、心も身体も鉛のように重く、目の前に霞がかかったような毎日を過ごしています。「悲しみに暮れる」という言葉がありますが、ある日を境に大切なものが目の前から消えてしまうことの悲しみに対して、たぶん僕たちは永遠に慣れることはできないのだと思います。暮れる日を来る日も来る日も見送り、ふと顔を上げて見る世界の美しさに、通り過ぎる春の風に、はっとさせられる瞬間を繰り返しています。気がつけば季節がひとつ前に進んでいた。そんな春でした。
長野県松本市の藤原印刷が主催する「心刷祭」というイベントに誘われ、特急あずさに乗ったのは、どちらかといえばそんな日々で家にいたくなかったからという理由でした。でも電車が甲府を過ぎた後に見えた雪をかぶった南アルプスの麓の里山の風景に目を奪われて、僕は急に「いつまでも沈んでいてはいけない」と目が覚めるような気持になりました。それは天国みたいな景色だったのです。もしかしたらその美しい場所のどこかに死んだ猫がいて、僕にそう伝えてくれたのかもしれません。そうだったらどれだけ素敵だろう。
藤原印刷はその印刷物の美しさと丁寧な仕事ぶりに、業界内外に多くのファンがいる松本の印刷会社です。「心刷」というのは心で刷るという藤原印刷のフィロソフィーを体現する言葉で、心刷祭は出版社だけでなく、高円寺の銭湯小杉湯(グッズを印刷しているそう)、唐辛子の八幡屋礒五郎など、藤原印刷と関わりのある会社や人がブースを構える印刷会社のお祭りです。ほかにも工場見学ツアー、長野県名物のおやきの販売など、コロナで久しく見ることのなかった笑顔がそこには集まっていました。仕掛け人は藤原印刷の未来を託された若き藤原兄弟。弟の章次さんは僕にこう教えてくれました。
「これは社員の日でもあるんです。お父さんのしている印刷の仕事ってかっこいいんだよというところを、社員が家族に見てもらえる日になれば」
「印刷会社だって地域に賑わいを作れる。今日もカオスですけど、もっとカオスになっていったらおもしろいですね」。兄の隆充さんも笑います。
型破りな2人に見えますが、型破りというのは、あくまで型あってのもの。藤原印刷の印刷物は、写真はあるべき色味でプリントされ、文字の並びはさりげなく整然と、本のすばらしさを改めて教えてくれます。
会場で1冊の絵本に出会いました。それはクルミド出版の新刊「うさぎのクーモ」。すべての絵が銅版画で描かれた美しい本でした。主人公の女の子が大事に飼っていたうさぎのクーモが死んでしまう所から物語は始まります。そしてある満月の夜、主人公は湖の中州でクーモに再会します。その物語は、今の自分とシンクロするものでした。多分そんなに簡単に奇跡なんておこりませんが、奇跡を信じる権利を放棄したくないので、僕はこれを奇跡だと思っています。
その銅版画の美しさ、そして物語全体に通底する夜の静けさの気配、選ばれた言葉の繊細さ。そこには1冊の本に向かって、銅版画家と文筆家、そして出版社の思いが帰結していった気配があり、その情熱を受け止めるだけの印刷技術がありました。まさにそれは本というフォーマットでなくては表現できないものだと感じます。
1枚の銅版画の制作に3カ月かかったと、内木場さんは話してくれました。効率的にゴールにたどり着くことが「善」とされがちな世界で、その「時間のかけかた」は、もはや異常レベルかもしれません。でもそのプロセスがその本からはしっかりと伝わってきた。少なくとも僕はその本を死ぬまで手放さないと誓いました。それを考えたら、その遅さは別に遅くない。
誰かの悲しみに寄り添える本がある。そして本というのは、誰かの悲しみに寄り添えるものである。その事実をあらためて教えてくれた藤原印刷とクルミド出版に、僕は感謝しています。そして今度は自分が作るもので誰かの悲しみに寄り添うことができたら。そう願って言葉を紡いでいます。
※メトロミニッツ2023年6月号より転載