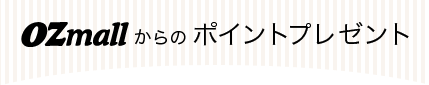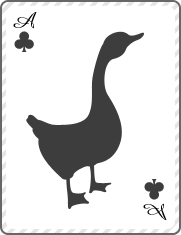雪国の春に、甘い憧憬を抱いてはいけない・・・!
日本でいちばん冬の終わりを願い、雪どけを祈り、誰よりも春の到来を待ちわびているエッセイストの北大路公子さん。雪国暮らしの身辺雑記の名手がつづる、幼き日の思い出とは。
雪どけの季節にあふれ出るものは
雪国の春は汚い。
春といっても花などまだ遠い時期、木々は裸で、空は重く、道端に残った雪がようやく嵩(かさ)を減らす頃である。
その雪の下から、様々な物が現れる。空のペットボトルやお菓子のパッケージ、破れた軍手に謎のビニール袋、そして今ならマスクの残骸。まあ、端的にいってゴミであるが、それらのゴミが芽吹くように一斉に姿を現すのが雪国の早春なのだ。
子供の頃から「嫌な季節だなあ」と思っていた。白一色だった街が茶色く殺風景に、道路脇の雪は泥と粉塵で真っ黒になる。通っていた小学校は片道三十分かかったが、未舗装の道路は雪どけが進むとひどくぬかるんだ。その粘ついた泥の感触も嫌いだった。
一度、そんなぬかるみに足を取られて、派手に転んだことがある。学校からの帰り道、ランドセルごと泥の中に倒れ込みながら、
「何もかもが嫌」
と、子供心に世の中を呪ったのを覚えている。髪の中まで泥だらけで、起き上がる気力もない。なんとか立ち上がったのは、泥の中の何かと目が合ったからだ。近づくと、小さな熊のマスコット人形だった。私と同じく全身どろどろで、丸い目だけがなぜか光っている。
「どうしたの? あんたも転んだの?」
思わず声をかけた。熊は何も言わない。
「冷たかったね」
なんだか他人とは思えず、私はそれを家に持ち帰り、きれいに洗ったのである。
風呂上がりの熊は、優しい顔をしていた。両足を投げ出すようにして座り、手はまるで何かを抱きしめるように大きく前へ広げている。一体何を抱きしめていたのだろう。おもちゃだろうか、花束だろうか。想像しているうちに、ふと思いついた。
「ひょっとして子熊かもしれない」
これは母熊で、小さな赤ちゃん熊とずっと一緒にいたのだ。でも泥に落ちた拍子に離れてしまった。今も赤ちゃん熊は泥の中だ。
そう考えると、胸の奥がざわざわした。当時の我が家には、赤ん坊がいた。生まれたばかりの歳の離れた妹で、ふにゃふにゃの妹が泥の中の赤ちゃん熊と重なる。
いてもたってもいられず、翌日から私は学校の行き帰りに、赤ちゃん熊を捜すことにした。転んだ現場に立ち寄り、雪どけのぐちゃぐちゃ道を覗き込む。けれども目につくのはゴミばかりだ。空き缶、吸い殻、半分凍った布きれ、片方だけの靴。雪の下からは無尽蔵にゴミが湧き出る気がした。だからこの季節は嫌なんだと悲しくなる。何日捜しても、結局、赤ちゃん熊は見つからなかった。
捜索をやめた日、家にあった余り布でてるてる坊主を作り、母熊の腕に抱かせた。赤ちゃん熊のかわりだ。サインペンで描いた目が滲(にじ)んで、まるで泣いているように見える。
「ごめんね」
誰にともなくそう言う。母熊はやっぱり無言で、見知らぬてるてる坊主をただ愛し気に抱きしめていた。
あれから半世紀近くの時が流れた。私もすっかり歳をとり、今でも雪の下からは大量のゴミが現れるが、その中に赤ちゃん熊がいればいいなとこっそり思うのである。
北大路公子
きたおおじきみこ 文筆家。北海道札幌市生まれ、在住。著書に『最後のおでん』(寿郎社)、『生きていてもいいかしら日記』(PHP文芸文庫)、『石の裏にも三年』『晴れても雪でも』(集英社文庫)、『ロスねこ日記』(小学館)など。最新作は連作短編小説『ハッピーライフ』(寿郎社)
PHOTO/SAORI KOJIMA
※メトロミニッツ2022年5月号特集「水のこと、考えてる?」より転載