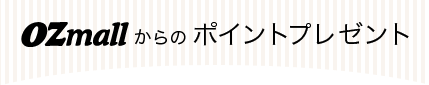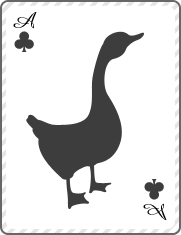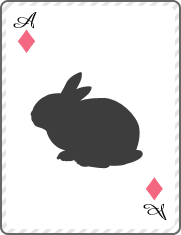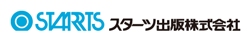寿司屋の貝がことのほか旨いのは、なんといっても旬のネタに丁寧な仕事をほどこしているから。酒場エッセイの名手・大竹聡さんが、浅草の名店でおすすめされるがまま、貝づくしの夜を楽しみます。 貝で、飲む。なかなかオツなものですよ。

浅草の老舗、紀文寿司を訪ねて貝づくしの夜
貝は冬から春先がうまいよ。そう教えてくれたのは、寿司職人だった。もう20年ほど前のことで、それ以来、冬が来ると貝をつまみに、酒を飲みたくなる。今年は、浅草の老舗、紀文寿司を訪ねて、貝づくしで飲みたいと無理を頼んだ。
ネタはお任せ、何が出てくるかワクワクしながらまずはビールに口をつける。
スタートは、煮ホタテだ。軽く茹でたホタテの貝柱にツメと呼ばれる煮詰めたタレをかけてある。ふんわりとして、ほどのいい甘さが嬉しい。膨らみがあるのに歯ごたえもよく、産地を聞くと、北海道は厚岸(あっけし)とのこと。1品目から、大袈裟を承知で言えば、目を瞠るうまさ。先行きへの期待が一気にふくらむ。

言葉が出ないほど旨い。ただ酒をあおるのみ
そこへ供されたのは、赤貝の肝。貝らしさを凝縮した香りと味に早くも衝撃を受けて、思わず日本酒を注文。銘柄は灘の辛口、菊正宗。これを燗でもらう。貝の肝の強い味わいに一口目の燗酒の刺激が絶妙に合う。文句なし。ご主人の関谷吉紀(せきやよしのり)さんは、創業明治36(1903)年というこの店の五代目で、店に伝わる江戸前寿司の伝統を継承している。赤貝も、祖父の頃には東京湾のものを一斗缶で大量に仕入れていたんですよと、笑う。ちなみに、今夜の赤貝は、宮城は閖上(ゆりあげ)産である。
続きましては北海道長万部(おしゃまんべ)べの北寄貝(ほっきがい)。これを炙ってくれた。サクサクとした歯ごたえ、味はというと、噛むとすぐに甘みが出てくる。貝は魚のように脂がのってうまくなるというより、筋肉が大きくなり、アミノ酸も増えてくる時期にうまみが増す。噛むほどに、じわりと口に広がるうまさには、言葉が出ない。だから、ただ、酒を飲むだけ。これで万全なのだ。完璧だな、と思うのだ。

やはり炙った平貝(たいらがい)はほんのり醤油の香りがして、それを焼き海苔で巻いていただく。貝と海苔という磯の香の競演。じわりと慈しむような豊かな味わいを楽しめば、酒をお代わりするのは当然。新規の徳利を傾けつつ、手元ばかり見ていた視線を店内に向けてみる。昭和30年頃の建築という店の中は、浅草の賑わいとは別物の、しっとりとした静かな空気に満ちている。忙しく手を動かすご主人の姿を目で追いながら、ふと、寿司っていうのは、海を味わうものなんだなと、思う。とりわけ貝は、豊かな磯や浜を思わせ、海をつまみに酒を飲むという、オツな気分にさせてくれる。

青柳(あおやぎ)は、湯通ししたものと、串を打って焼いたものとが出た。前者から先に味わう。青柳の軽い草の匂いが口腔に広がり、鼻に抜け、焼いたものからはさらに凝縮したうまみと香りがもたらされた。子供の頃、千葉の内房は富津(ふっつ)で食べた青柳もうまかった記憶があるが、この香りと味わいはやはり、酒と合わせてこそ、と思う。

さあ、ここで合いの手が入った。蛤を煮た汁を調え、三つ葉をぱらりと垂らした見事なお椀という合いの手だ。うまいねえ…。やさしく、深く、人を元気にしてくれるお汁。酒で少しぼんやりしかかっている頭の靄がすっかり晴れ、舌は完全に更新される。

赤貝の握りに、感動と活力をもらう
そして、ここからは、握りの時間。まずは赤貝。煮切り醤油をさっと塗ったネタは、少し硬めのシャリの上にのっている。このシャリの米の炊き具合や酢の加減にはただ感服するばかりで、ここまで貝づくしで酒を楽しんできた味覚と嗅覚に、握りならではの確かな感動を与えてくれるのである。アスリートの活躍について人はよく勇気をもらったとか口にするけれど、私にとってはこの一貫の赤貝の握りはまさに、活力の源になった。なにしろ、これほどうまいもの、昨今、食べてないよなあ、と思ったくらいだから。

先ほど、頭がぼんやりするくらいに、その味と香りを堪能した青柳の、小柱が出てきた。これは貝柱を軍艦巻きにしたもので、寿司屋で貝を、と思ったとき同時に思い浮かべるほど好きな逸品。口を開け、さっと放り込んで、爽やかさと磯の香を思う存分に味わう。

さらに、畳みかけてきたのが蛤の握り。この握りが苦手という人は、広い日本に、ひとりもいないのではないか。と、思わせる万全の食感。ふわりとしているのに、身は締まり、貝そのものの甘みをツメが包んでさらに奥深いものにしている。

握りにたどり着いた後はさっさと食べてお茶を啜るのが普通かと思うけれど、なにしろ軽い興奮状態になっていて、酒が止まらない。さらに1本頼んでいると、締めの海苔巻きが出た。赤貝のヒモとキュウリを海苔で巻いたもの。これもまた、深いうまみと軽さが身上。海苔巻きなのに、唸るほどうまいから驚きますよ。
いかがでしょう。貝づくし10品で、じっくりと酒を味わう。真冬の夜に、凍てつく夜に、腹の底から温まりますよ。

【取材風景より】左/紀文寿司五代目の関谷吉紀さん。ほれぼれするほど鮮やかな仕事ぶり 右上/趣ある店奥の壁には、往年の築地仲卸の札や寿司桶 右下/店外の看板で目を引く「登録商標」の文字。先々代が洒落で登録したのだとか

紀文寿司
TEL.03-3841-0984
住所/東京都台東区浅草1-17-10
営業時間/12:00~14:00、17:00~21:00(20:00LO) 日・祝12:00 ~ 19:00
定休日/水

文・大竹聡
おおたけさとし 1963年生まれ。作家、ライター。ミニコミ誌『酒とつまみ』創刊編集長。『中央線で行く東京横断ホッピーマラソン』『酔っぱらいに贈る言葉』(ともに、ちくま文庫)ほか著書多数
PHOTO/KEIGO SAITO
※メトロミニッツ2022年1月号特集「新・日本さかな風土記」より転載