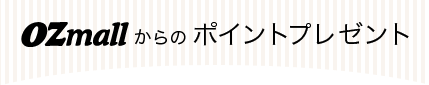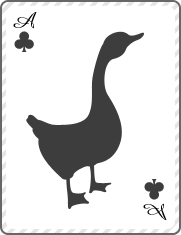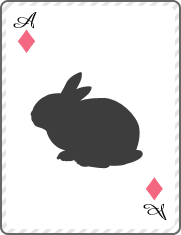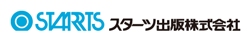人気の幼児通信教育おすすめ10選を比較!受講するメリットや選び方も解説

小学校入学前の自宅学習に活用できる、幼児通信教育。手軽に始められるとして人気があるものの、紙媒体のものからタブレット教材まで種類が豊富で、算数や英語、生活習慣など学習内容もさまざま。どれを選べばよいか迷っている人も多いのでは? そこで今回は、編集部が選んだ幼児通信教育おすすめ10選や選び方のポイントを紹介。比較しながら、我が子にぴったりの教材を選んでみて。
更新日:2025/05/21
※アフィリエイト広告を含むPR記事です
1.幼児期の通信教育の必要性は?メリットや期待できる効果について解説
就学前の幼児通信教育は本当に必要なのか、疑問に感じている人もいるはず。まずは、幼児期から通信教育を始めるメリットや、期待できる効果について詳しく解説。

脳の発達が著しい時期に多くのことを学べる
近年の脳科学の研究においては、人間の脳は3歳で約80%、6歳で約90%まで完成すると言われている(※1)。脳の成長期ともいえる幼児期に通信教育を取り入れることで、より多くのことを吸収しやすい。
幼児教育においては、やみくもに知識を詰め込むのではなく、脳の部位ごとの発達に合わせた学習を取り入れるのが望ましい。例えば、感覚が発達する0歳頃には、触覚を刺激する教材や母国語の習得にかかわる学習がおすすめ。いろいろな疑問が湧いてくる2~4歳の時期には、図鑑などで知的好奇心を刺激するのも効果的。
通信教育は子供の脳の発達に合わせて段階的に教材が作られている場合が多く、子供にとって無理のない学習をめざせる。
※1 出典:SCAMMON R.E.(1930)The measurement of the body in childhood.

小学校入学前に基礎学力や学習習慣をつけられる
幼児通信教育を利用することで、小学校入学前に基礎学力をつけておける。入学してから授業についていけず、勉強に対して苦手意識を持ってしまう事態を防げる。
また、自宅での学習習慣をつけられるのも魅力のひとつ。毎日少しずつ勉強する習慣をつけておけば、小学校入学後も宿題への取り組みがスムーズになるはず。

幼児教室などの習い事と比較して費用を抑えやすい
通信教育は、塾や幼児教室などの習い事へ通う場合に比べ、費用を抑えやすい。習い事に通うと、月々5千円~1万円程度の月謝が負担となりがち。通信教育は月々3千円以下で始められるものもあり、コスパよく学べるのがメリット。
また、自宅で取り組めるので送迎の手間もかからない。仕事が忙しくて習い事の送迎が難しい家庭にはうってつけ。

家庭での隙間時間を活用できる
幼児通信教育は取り組む時間を自由に決められるので、親子ともに無理のないスケジュールで進められる。子供がやりたいと思ったタイミングや、親の隙間時間を活用して学べるのは魅力的。負担がかかりにくいため、長く続けやすい。

親子のコミュニケーションツールにもなる
自宅で過ごすことの多い幼児期には、通信教育が親子のコミュニケーションツールになる。ワークだけでなく、読み聞かせに使える絵本や知育玩具が届く場合も。子供と一緒に取り組むことで、学習状況を把握できるだけでなく、愛着形成にもつながる。
2.幼児通信教育の選び方
幼児通信教育を選ぶときに注目したい、4つのポイントをご紹介。

1歳から?3歳から?対象年齢を確認しよう
同じ幼児通信教育と呼ばれるものでも、対象となる年齢はさまざま。3~4歳からの学習に特化したものや、幼稚園入園前の2歳から利用できるものがある。なかには0歳から始められる通信教育もあるので、早期から取り組みたいと考えるならチェックしてみて。

難易度やコース内容が子供に合っているかチェック
長く継続させるために、教材の難易度が我が子に合っているか確認しよう。難しすぎると子供の学習意欲を低下させる恐れがあり、逆に簡単すぎると興味を持てなくなることがある。
楽しく学ぶことをメインにした難易度が低いもの、受験対策に使える高難易度のものなどさまざまなので、目的に合わせて選ぶようにして。資料請求や体験版で教材のサンプルを取り寄せておくと、事前に難易度を確認しやすい。

紙かタブレットか使用する教材の種類で選ぶ
幼児通信教育には、紙のワークを中心に取り組むタイプと、タブレット学習をメインとするタイプの2種類がある。紙ワークは、自分で読み書く動作を通して、記憶を定着させたり読解力をつけたりできるのがメリット。手先を動かすことで、脳の感覚機能の発達も促せる。
タブレット学習は、ゲーム感覚で楽しく学べる点や、場所を問わずに取り組みやすい点が魅力として挙げられる。近年では小学校の授業でもタブレットを使用するため、操作に慣れておけるメリットも。どちらの長所も取り入れたいなら、紙ワークとタブレットの両方を採用している幼児通信教育を検討しよう。

無理なく続けられる料金であるかも重要
幼児通信教育は継続することが大切なので、料金が無理なく支払える範囲であるか確認しよう。子供の教育に当てられる月々の予算をふまえて、収まる通信教育を選ぶのがおすすめ。
なかには1年分を一括前払いすることで、受講費がお得になるところも。続けられるか不安に思う場合は、退会や解約に手数料がかからないかどうかもチェックしておくとよい。
3.【編集部おすすめ】人気の幼児通信教育10選
スマイルゼミ 幼児コース
専用タブレットで学ぶ楽しさを子供に届ける。続けたくなる通信教育
幼児の学びを楽しく変えるスマイルゼミは、専用タブレットで算数や国語の基礎を直感的に習得可能。書き順や筆圧をガイドする機能により、文字学習もスムーズに進められる。正しい書き方を学びながら自信をつけることで、自主的な学びを後押しする。
タブレット1台に豊富な教材を収録し、毎日取り組むべき内容を自動で提案。短時間でも集中して取り組める設計で、子供の「もっと学びたい」を引き出す。親子で成果を共有し、達成感を得られるシステムも魅力のひとつ。
月ごとに配信される講座や過去の教材を、いつでも自由に学習できる点もポイント。学齢にかかわらず、子供の理解度に合わせて先取りもできる「無学年学習」でどんどん進められる。約2週間の体験入会も可能なので、まずはお試しから始めてみては。
| 対象年齢 | 3歳~6歳 |
|---|---|
| コース | 年少~年長コース、英語プレミアム |
| 月額料金 | 4378円、英語プレミアム:869円(税込) ※毎月払いの場合 |
| 入会金 | 10978円(税込) ※タブレット代金 |
| 学べる内容 | ひらがな、数、ことば、かたち、英語、生活、知恵、自然 |
| 学習スタイル | タブレット |
| 無料体験 | あり(2週間) |
| 学習管理機能 | 学習内容や正答率を確認できる「みまもるネット」 |
こんな人におすすめ
・タブレット1台で取り組める通信教材がほしい
・幼児期から英語も学ばせたい
・無学年学習で先取りしながら進めたい
こどもちゃれんじ
絵本、おもちゃ、映像など多様な教材で、しまじろうと一緒にチカラを育む
0~6歳の発達に寄り添う幼児教育教材で、しまじろうとともに楽しみながら、知育、体験、情緒教育を総合的にサポートする。一生役立つ力を育むプログラム設計になっていて、子供の好奇心をぐんぐん引き出す。
子供の成長段階に応じた教材が、毎月お届けされる仕組み。絵本やおもちゃ、映像教材などの多彩なツールで、言葉、知育、生活習慣などの学習に取り組める。遊びながら学べる楽しさを実現し、学習だけでなく親子の絆を深めるのにも役立つ。
教育のプロが監修したカリキュラムにより、安心して取り組める内容に。教材の多様さと品質の高さから、多くの家庭で支持される幼児教育の定番。未来を育む最初の一歩としておすすめ。
| 対象年齢 | 0歳~6歳 |
|---|---|
| コース | こどもちゃれんじbaby、ぷち、ぽけっと、ほっぷ、すてっぷ、じゃんぷ |
| 月額料金 | baby:2310円、ぷち・ぽけっと:2990円、ほっぷ・すてっぷ:2390円~、じゃんぷ:3290円~ ※毎月払いの場合 |
| 入会金 | なし |
| 学べる内容 | 色彩、感覚、ことば、運動リズム、生活習慣、ひらがな、カタカナ、数、英語、生活、自然、表現、プログラミングなど |
| 学習スタイル | ほっぷ・すてっぷ:デジタルスタイル or ハイブリッドスタイル、じゃんぷ:タブレット or 紙教材 |
| 無料体験 | あり |
| 学習管理機能 | 保護者用サポートアプリ、学習内容のメール通知 |
こんな人におすすめ
・0~1歳から発達に合わせた通信教材を取り入れたい
・絵本やおもちゃで楽しく学びたい
・教材の質もコスパのよさも重視したい
Z会幼児コース
体験型教材とワーク学習で、好奇心を刺激しながら考える力を育む
「Z会の通信教育 幼児コース」は、年少から年長を対象に、体験型教材とワーク学習を通じて学ぶ楽しさを提供する。小学校入学以降の「あと伸び力」を育むため、幼児期に興味や好奇心を持てるような教材設計が特徴。五感を使った体験を重視し、みずから考える力を養うプログラムを展開している。
体験型教材の「ぺあぜっと」では、観察や体感などができる内容で子供の好奇心を刺激。「かんがえるちからワーク」では、言葉や数などさまざまな領域を鍛える問題が揃い、粘り強く考える力を育む。親子で楽しみながら、挑戦、発見、創造のサイクルを築く教材が充実している。
教材は年齢に応じて最適化され、小学校入学後の学びにも対応。資料請求やお試し教材の体験も可能で、家庭での学びをより楽しく、充実したものにしてくれるはず。
| 対象年齢 | 3歳~6歳 |
|---|---|
| コース | 年少~年長 |
| 月額料金 | 年少:3500円、年中・年長:3980円(税込) ※毎月払いの場合 |
| 入会金 | なし |
| 学べる内容 | ひらがな、数、形、生活、自然、表現、など |
| 学習スタイル | 紙教材 |
| 無料体験 | あり(お試し教材) |
| 学習管理機能 | - |
こんな人におすすめ
・考える力を伸ばし、小学校以降の学習に備えたい
・体験型教材も取り入れたい
ワンダーボックス
デジタルとアナログが融合した「STEAM教材」でわくわくを引き出す!
4歳から10歳を対象に、科学、技術、工学、芸術、数学の5領域を重視した「STEAM教材」を毎月お届け。子供の好奇心を刺激しながら、論理的思考力や創造力を養う。
アプリ教材とキット教材を組み合わせ、多彩なテーマで学びをデザイン。アプリ教材では、プログラミングや物理実験、アートなどを楽しく学べる。キット教材では、実験ができるトイ教材をはじめ、紙と鉛筆でやるからこそ意義がある思考力問題にも挑戦可能。
また、保護者向けのサポートも充実し、子供の作品や挑戦の記録を閲覧できる機能を搭載している。アプリには使用時間を制限できる「おやすみ機能」もあり、集中力や目の健康にも配慮。子供の好奇心を刺激しながら、論理的思考力や創造力を養いたいなら要チェック。
| 対象年齢 | 4歳~ |
|---|---|
| コース | ジュニア、ジュニアプラス |
| 月額料金 | 4200円(税込) ※毎月払いの場合 |
| 入会金 | なし |
| 学べる内容 | プログラミング、数理パズル、アート、理科実験 |
| 学習スタイル | 紙教材、タブレット、キット教材 |
| 無料体験 | あり |
| 学習管理機能 | 保護者向け情報サイト、学習内容や作品の閲覧 |
こんな人におすすめ
・子どもが科学やプログラミングに興味を持っている
・理系科目に特化した教材がほしい
・キット教材も使った実践的な学びがほしい
RISUきっず(RISU算数)
算数を楽しく学んで、未来をつくる思考力を
年中後半から年長を対象に、算数の基礎を楽しく学べる幼児向けタブレット教材。身近なテーマを活用し、数の概念や足し算、引き算を無理なく習得できる。タブレットの音声読み上げ機能や豊富なイラストで、ひらがなが不安な子供でも楽しんで学べるように。
学習状況はデータ管理され、東大生などのチューターがピンポイントでフォロー。つまずきやすいポイントをサポート動画でカバーし、復習テストで定着を図る。学習のモチベーションを保つ「がんばりポイント」や景品交換制度も充実。ゲーム感覚で楽しみながら、算数力と論理的思考力を伸ばす。
さらに、無料の英語レッスン動画「RISUきっずEnglish」も提供。算数の復習を英語で行いながら、英単語や英文に親しめる。タブレット費用は無料で、最短3日後から利用が開始できる。
| 対象年齢 | 4歳~6歳 |
|---|---|
| コース | - |
| 月額料金 | 2948円(税込) ※毎月払いの場合 |
| 入会金 | なし |
| 学べる内容 | 算数、英語 |
| 学習スタイル | タブレット |
| 無料体験 | - |
| 学習管理機能 | 独自システムによる学習データの分析 |
こんな人におすすめ
・小学校入学前に、算数の基本を身につけたい
・子どものモチベーションを保つお楽しみコンテンツもほしい
・手持ちの端末はないが、タブレット学習をさせたい
天神
才能と個性を育てる、タブレット型の無限学習
0歳から6歳までの学習内容を網羅したタブレット教材で、知識、数量、言葉、記憶、思考の5系統63ジャンルが、約10000問収録されている。特許取得のカリキュラム自動調整機能により、学習状況や成長に合わせて内容が最適化される仕組み。子供の発達や興味に応じて、自由にカリキュラムを組める。
フラッシュカードや読み聞かせ、ゲーム形式の問題で、学ぶ楽しさを実感可能。「シール」をためてイラストを完成させる機能もあり、達成感とモチベーションを維持できる。1問1答形式で褒めながら進行するため、短時間でも集中力を引き出しやすい。
利用にはネット接続が不要で、オフライン環境でも学習を進められる。学ぶ範囲を制限せず、子供の「好き」という気持ちや個性を活かしながら、好奇心と才能を伸ばす「才育型」の教育をかなえたい人は、無料体験もチェックしてみて。
| 対象年齢 | 0歳~6歳 |
|---|---|
| コース | 幼児タブレット版 |
| 月額料金 | 資料請求後に開示 |
| 入会金 | 資料請求後に開示 |
| 学べる内容 | 知識、数量、ことば、記憶、思考 |
| 学習スタイル | タブレット |
| 無料体験 | あり |
| 学習管理機能 | - |
こんな人におすすめ
・外出先でも困らない、オフラインで学習できるタブレット教材を探している
・0歳から始められる通信教材がほしい
・ゲーム感覚で楽しく学ばせたい
がんばる舎 すてっぷ
親子で一緒に取り組める紙教材で、学習への興味を引き出す
幼児期に大切な学びの基礎を、親子で楽しく始められる紙教材。月額制の始めやすい価格設定で、ひらがなや数の概念、形の認識など、発達に応じた内容を6コースで提供。鉛筆やクレヨンを使うことで、手先の器用さや筆圧の感覚も自然に養われる。
教材は親子で一緒に取り組む設計になっており、日常の体験を活かして学びを深められるのが特長。問題を解く前に親子で話をしたり、葉っぱを数えるなどの遊びを通じて学習への興味を引き出す。無理なく楽しく進めることで、子供の「もっと知りたい」「もっとやりたい」を引き出す工夫が盛りだくさん。
さらに、別冊の解答集で一緒に答え合わせをすることで、子供と達成感を共有できる。集中力や記憶力を育てながら、親子の絆も深められるはず。オプション教材も用意されており、さらに学びを広げたい家庭におすすめ。
| 対象年齢 | 2歳~6歳 |
|---|---|
| コース | すてっぷ |
| 月額料金 | 1090円(税込) ※毎月払いの場合 |
| 入会金 | なし |
| 学べる内容 | 言葉(ひらがな、カタカナ)、数・量、図形、記憶、知識、作業など |
| 学習スタイル | 紙教材 |
| 無料体験 | - |
| 学習管理機能 | - |
こんな人におすすめ
・紙教材で書く力や手先の器用さを伸ばしたい
・月額料金を抑えながら続けたい
・親子で楽しく取り組める教材がほしい
モコモコゼミ
ハイレベルだけどかわいく楽しく、確かな学力を育む
幼児教育で定評のある「こぐま会」の教材を基にした通信教育。思考力や表現力を養いながら、小学校入学前には文字の読み書きや四則演算の基礎まで、無理のない習得をサポートする。
教材は冊子やカード、パズル、シール、ぬりえなど多彩。内容はハイレベルながら、かわいらしいキャラクターで子供の興味を引き、楽しみながら取り組める。オンラインオプション「モコモコちゃんねる」も用意され、キャラクターが冊子の問題を読み上げる、答え合わせするなどで学習を手伝ってくれる。
また、小学生コースとして「SAPIX(サピックス)の通信教育 ピグマキッズくらぶ」と提携しており、中学受験を見据えた学習にも対応。途中解約も無料で柔軟に対応しているため、気軽に始めやすいのも嬉しい。将来を見据えた学びの第一歩に。
| 対象年齢 | 1歳~6歳 |
|---|---|
| コース | プチコース、プレコース、年少コース、年中コース、年長コース、算数強化トレーニング |
| 月額料金 | プチコース:1738円、プレコース~年長コース:3278円~、算数強化トレーニング:1991円(税込) |
| 入会金 | なし |
| 学べる内容 | ことば、数、形、思考、算数 |
| 学習スタイル | 紙教材 |
| 無料体験 | あり |
| 学習管理機能 | 保護者用チェックシート |
こんな人におすすめ
・小学校入学前に、読み書きや四則演算を無理なく身につけたい
・かわいいキャラクターの教材で子どもの興味を引きたい
幼児ポピー
カラフルで楽しい誌面でわくわく学べる!特別教材も充実
幼児期に大切な「こころ」「あたま」「からだ」をバランスよく育てる。カラフルで楽しい誌面やシール遊びなどを通して、文字、数、言葉の基礎を無理なく学べる設計が特長。デジタル教材やダウンロードプリントも活用して、学びをさらに深められる。
教材には、親子のふれあいを深めるミニ絵本や、ごっこ遊びを促す季節の特別教材などが含まれ、家庭での学びをより充実させる工夫が満載。「思考力めばえ わぁくん」や「もじ・かず・ことば ドリるん」で段階的に小学校入学準備も進められ、英語アニメーション「にこにこ えいご」で語学への関心も育てられる。
付録を省いたシンプル設計で、費用を抑えつつ続けやすい点も魅力。さらに、プレゼントキャンペーンや初月割引キャンペーンなど、お得に始められるキャンペーンを随時開催している。親子の時間を大切にしながら、幼児期の学びをサポートしてみては。
| 対象年齢 | 2歳~6歳 |
|---|---|
| コース | ももちゃん(2~3歳)、きいどり(年少)、あかどり(年中)、あおどり(年長) |
| 月額料金 | 1500円(税込) ※毎月払いの場合 |
| 入会金 | なし |
| 学べる内容 | 生活習慣、文字、数、言葉、思考力、運動、英語 |
| 学習スタイル | 紙教材、デジタル教材 |
| 無料体験 | あり |
| 学習管理機能 | - |
こんな人におすすめ
・文字や数、思考力などをバランスよく伸ばしたい
・月額料金を抑えたい
・シンプルな通信教材を探している
学研通信講座
学びの未来をつくる、信頼の通信講座
学研通信講座の幼児向けコース「もじ・かず・ちえ」は、ひらがなの読み書きや数の概念、思考力などを育み、幼児期の総合的な学習をサポート。あえて学年ではなく「級」の表示にし、わかるところから学習を積み上げられる教材で、基礎から応用まで無理なく学べる。
学研教室オリジナル教材を使用し、幼児から中学生まで系統的に学習できる内容。完全担任制で、月約2回のやり取りを通じて、個々の習熟度に合わせたきめ細やかな指導を行う。教材は100点になるまで担任が繰り返し添削し、理解度の定着を図るのも特徴。
さらに、保護者との連絡ノートを通じて、学習状況の報告やアドバイスなども伝えてくれるなどサポートが充実。FAXや郵送での質問受付、提出ポイントに応じたプレゼント制度など、1人でも続けられるさまざまな仕組みも整っている。
| 対象年齢 | 5歳~6歳 |
|---|---|
| コース | さんすう・こくご、さんすう・こくご・えいご |
| 月額料金 | さんすう・こくご:7810円、さんすう・こくご・えいご:12650円(税込) |
| 入会金 | 5500円(税込) |
| 学べる内容 | 文字、数、知恵、英語 |
| 学習スタイル | 紙教材 |
| 無料体験 | - |
| 学習管理機能 | - |
こんな人におすすめ
・幼児期から国語、算数、英語の基礎をしっかり身につけたい
・個別の添削指導を受けたい
・きめ細やかなサポートを求める
4.年少からでは遅い?幼児通信教育を始めるのにおすすめの年齢

人間の脳は3歳までに急成長すると言われている(※2)ため、年少となる3歳までに始めるのがおすすめ。しかし、3歳を過ぎても子供の脳はさらに成長していくため、年少以降でも遅すぎるということはない。
2~3歳頃までは音や色に触れて豊かな五感を養うような体験型の学びを、言葉への理解が深まる3~4歳以降は手先を使って取り組む学びを取り入れていきたい。
※2 出典:SCAMMON R.E.(1930)The measurement of the body in childhood.
5.幼児通信教育に関するQ&A
Q.幼児にとって適切な1日あたりの学習時間は?
A.多くの幼児通信教育では、1日あたりの学習時間を10~20分程度として教材を作成しています。大切なのは多くの時間をかけることよりも、毎日少しずつ取り組むことなので、無理なく習慣づけるようにしてください。
Q.早生まれでも学習内容についていける?
A.個人差はありますが、よほど先取りするような教材でなければ問題ないことがほとんどです。特に子供の興味関心を養うような体験型の学習は、生まれ月にかかわらず楽しく取り組めるでしょう。少し難しいと感じる場合は、子供の様子を見ながら取り組むペースを遅らせるのもひとつの手です。
Q.英語は何歳から始めるべき?
A.言語の音や文法に対する柔軟性が高まる、3~7歳で始めるのがよいといわれています。幼児期から英語に触れて、いわゆる「英語耳」を身につけることで、自然な発音を習得できるでしょう。
Q.子供が嫌がらずに続けるコツは?
A.子供の学習意欲をキープするためには、親子で一緒に取り組むことが効果的です。大人がサポートし、一緒に楽しむ姿を見せることで、勉強の楽しさを学べます。
通信教育まかせになってしまったり、子供の間違いを過度に否定したりするのは逆効果となりかねないので要注意。「間違えても大丈夫」「もう一度やってみよう」など、子供の気持ちに寄り添う声掛けをしてみてください。
Q.タブレット学習は視力の低下につながる?
A.タブレットでも紙ワークでも、近くのものを長時間見続けると視力の低下を招くことがあります。大切なのは、タブレットと目の距離を30cm以上あけるようにすることや、30分ごとに休憩を挟むこと。子供はつい熱中して長時間画面を見てしまいがちなので、保護者が使い方や時間をしっかり管理するようにしましょう。