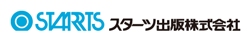「国立能楽堂」の舞台裏にOZが潜入!

千駄ヶ谷駅から徒歩5分、閑静な住宅街の中にしっとりとした和の趣を漂わせている「国立能楽堂」。早速、足を踏み入れると大きな屋根のついた能舞台が! 回りには白い小石が敷き詰められていて、松の木の植栽も。これは昔、能舞台が屋外にあった名残を留めているからだそう。それでは、「国立能楽堂」の舞台に関するあんなことから驚きの事実まで、一挙に公開!
画像出典: 「国立能楽堂」
更新日:2016/08/02
舞台の床板は尾州産檜、全部で10億円とも!!

4本の柱に囲まれ厳かな雰囲気に包まれた本舞台は、三間(約6メートル)四方の正方形。総檜造りで、床板は厚さ43ミリ、なかなか手に入らない貴重な尾州産檜のみを使用していて、今では値段も計算できないとか。
「鏡板」(かがみいた)には松の絵が描かれるのが決まり

本舞台正面奥の羽目板のことを「鏡板」と呼び、松の絵が描かるのが決まり。「国立能楽堂」の鏡板には神聖な老松が描かれているが、老松の姿はそれぞれの能楽堂によって異なる。また向かって右側、竹が描かれた面には「切戸口」(きりどぐち)と呼ばれる小さな出入口があり、地謡(じうたい)=コーラス役や後見(こうけん)が出入りする。
演者が登場する花道「橋掛リ」(はしがかり)と揚幕(あげまく)

舞台に向かって左手斜めに延びている部分が「橋掛リ」。ここは、演者が登場する通路だけでなく、演技空間としても使われる。橋掛リの奥に下がるカラフルな幕は「揚幕」と呼ばれ、地・水・火・風・空を表す5色に色分けしてある。さらに、橋掛リ沿いに松の木が植えられているのも見逃さないで。本舞台に近い側から、一ノ松、二ノ松、三ノ松と呼ばれ、だんだん丈が低くなり遠近感を出している。
初公開! 本舞台側から客席を望む

今回特別に、舞台の上を歩かせていただいたOZの取材陣。初めて演者側から眺める視界は本当に新鮮! ここで気を付けなければいけないのが、足袋を履かないと舞台には上がれないこと。それだけ神聖な場所だという証。さらに、摺り足で歩くことも基本。立ち居振る舞いが美しく見えるのと同時に、舞台に余分な音を立てないためだそう。座席は、左から2ブロックが「正面」、真ん中2ブロックが「中正面」、右の2ブロックは「脇正面」。本舞台から眺めると、意外と客席までの距離が近いかも!?
演者さんの楽屋にOZが潜入!

6つ並んでいる楽屋は、手前からシテ方(主役を演じたりコーラス役の地謡などを演じる役柄)の3部屋、ワキ方(現実に存在する男性役を演じる役職)1部屋、狂言方(能においてはアイ=間と呼ばれる役を担当)1部屋、囃子方(笛、小鼓、大鼓、太鼓)の順。1間につき20畳もの広さの楽屋がずらっと並ぶ光景に感動! 廊下を挟んで、装束を身に着ける「装束の間」、面を着ける「鏡の間」と続く。