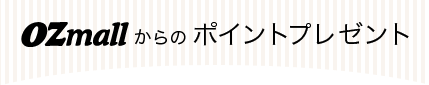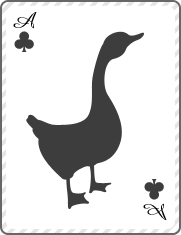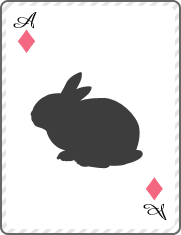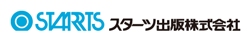【イベントレポート】日本の伝統芸能に触れる初めての能楽入門

「好き」を見つけて、私をもっと好きになるためのオズモール×東急グループのコラボプロジェクト「キラリプラスカレッジ」。第8回目のイベントが2019年2月9日(土)、セルリアンタワーで開催された。今回のテーマは「日本の伝統芸能に触れる 初めての能楽入門」。18名の参加者は、能楽に関する基礎知識を学んだのち、セルリアンタワー能楽堂で能楽を鑑賞。さらに、実際の舞台に上がる体験も。そんなイベントの様子をレポート!
更新日:2019/03/05

知ればもっとおもしろい!
能楽の歴史や楽しみ方をレクチャー
日本の伝統芸能である「能楽」。敷居が高く思われがちだけれど、もっと多くの人にその魅力に触れてほしい! そんな思いから企画された今回のイベント。会場は、渋谷駅からほど近いセルリアンタワー地下2階にある「セルリアンタワー能楽堂」。公演を鑑賞する前には、伝統文化ジャーナリストの氷川まりこ先生を講師に招いてトークセミナーを開催。初めて見る人にもわかりやすいよう、能楽のルーツや楽しみ方などが伝えられた。
「能と狂言を合わせて『能楽』といいます。能を見ていると眠くなってしまう・・・という方もいらっしゃいますが、能の独特な節回しには、脳がリラックスするアルファ波が出ると科学的に検証されています。だから、少しくらいなら寝てしまっても大丈夫!」という先生の言葉を聞いて、参加者も思わず笑顔に。
老舗料亭「金田中」による
旬の味覚たっぷりの軽食プレートも
能楽の公演は狂言と能、合わせて約150分。合間にお腹が空いてしまわないようにと、今回のイベントのために、セルリアンタワー東急ホテル内にある老舗料亭「金田中(かねたなか)」が特別な軽食を用意。
「ぶり蕪ら押し鮨」や「イイダコの桜煮」など、旬の食材を中心とした料理が盛り付けられたプレートは、見た目も華やか。どれも上品な味わいで、食べやすいひと口サイズなのも嬉しい。甘味として、江戸時代から伝わる料理で、牛乳とくず粉から作られた「漉し餡汁粉の峰岡豆腐」と抹茶も振る舞われた。
これだけは覚えておきたい能楽の基本

能と狂言の関係は?
“世界で最も古い舞台芸術”とも言われている能楽のルーツは奈良時代。もともとはひとつの芸能だったが、約650年前の室町時代頃に、歌や舞が中心でシリアスなストーリー展開の「能」と、セリフが中心で笑いの要素が盛り込まれた「狂言」に分かれたといわれている。そのため、能楽の舞台では、必ず能と狂言が同時に行われる。

舞台に立つ人の役割は?
能楽の舞台はすべて分業制。能で謡と演技を担当する「シテ方」、物語の進行役の「ワキ方」に加えて、狂言を演じる「狂言方」、音楽を担当する「囃子方」の大きく4つの役割に分けられる。また、シテ方の中でも主役を演じる「シテ」、そのほかの役を演じる「ツレ」などがあり、シテが舞台監督も務めることが多いそう。

能面は“無表情”ではない?
現在までに伝えられている能面の種類は約60から90種類。面の表情自体には動きはないけれど、うつむき加減になると寂しそうに見えたり、顔を上げると晴れやかな表情に見えたり。同じ能面もほんの少し角度を変えるだけでまったく違う表情に見えるので、物語の展開と合わせて注目してもおもしろい。
能楽を見るときはここをチェック!

シテに気持ちを重ねながら鑑賞しよう
能を楽しむうえで大切なポイントは、登場人物の気持ちを想像しながら見ること。「同じ演目を見ても、そのときの自分の感情や、演じる人が変わることで全く違う印象になるんですよ」と氷川先生。また、事前にあらすじを頭に入れておくと、言葉の言い回しが難しくてもストーリー展開が追いやすくなるので、開演前に一度目を通してみて。

【その1】優雅に見える動きは稽古の賜物
「ハコビ」と呼ばれる能楽の舞台の歩き方はすり足が基本。やや中腰の姿勢で膝を曲げ、踵を床から離さずにつま先だけを上げて歩く独特の技法は、実際にやってみると難しい! 体幹を鍛えることが重要で、おへその下に位置する丹田(たんでん)に力を入れて、ゆっくり足を進めるのがコツだそう。

【その2】屋内なのに舞台に屋根がある理由
能楽の舞台に屋根が付いているのは、もともとは屋外で行われていたことに由来。欄干のある渡り廊下の側に、高さの異なる3本の松の木が立てられたりと、屋外にあった頃の舞台が忠実に再現されている。また、シテ方は能面を付けると視界が狭くなってしまうため、舞台に立つ柱は目印としての役割もあるという。

【その3】舞台に描かれた松の木の意味
「鏡板(かがみいた)」と呼ばれる舞台中央の壁に必ず描かれているのが「老松(おいまつ)」。松の木は神様を象徴する木とされていたことから、神様に向かって舞を奉納するという意味が込められているという説や、奈良の春日大社に実在した「影向(ようごう)の松」をモチーフにしたという説も。

オズモールと東急グループのコラボプロジェクト「キラリプラスカレッジ」
自分の「好き」を追求していくと、知識が増えるのはもちろん、また別の分野へと興味が広がったり、没頭している時間自体がリフレッシュにつながったり・・・。ありのままの素の自分が磨かれて、私らしさもよりパワーアップ。オズモールと東急グループのコラボプロジェクト「キラリプラスカレッジ」では、「好きなコトで私をもっと好きになる」をキャッチフレーズに、私がキラリと輝くきっかけになるイベントを4回に渡って実施。ぜひチェックして!
PR/東急グル―プ
PHOTO/AYA MORIMOTO WRITING/MINORI KASAI