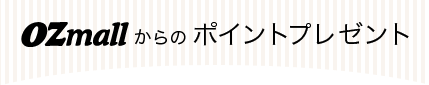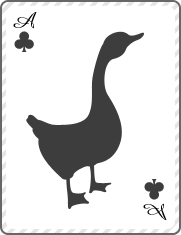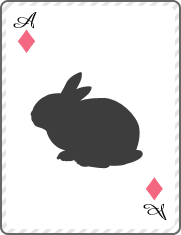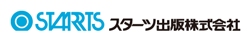注目の「キラリ企業」の福利厚生を深掘り! キラリと光る企業の福利厚生の取り組みが、ミライの人材育成に繋がっていると編集部は考えています。“従業員を大切にしたい”企業と“働きやすさ”を実感している従業員の“両想い”の関係が、福利厚生にも表れているはずだと。そこで今回は、美容機器メーカーのヤーマンにうかがい、社員の美と健康を支える「美容健康手当」を中心に、その背景や想いを直接インタビューしてきました。
お客様視点を大切に。社員に求める美容カテゴリへの愛着

編集部|山﨑さん、ヤーマンの事業に対する思いや理念についてお聞かせください。
山﨑さん|当社のスローガンは「美しくを、変えていく。」です。美容機器メーカーとして、美の常識をアップデートし、お客様の生活の質を向上させることをめざしています。私は社会人としてのキャリアを通してヤーマンで働いてきましたが、振り返ると、入社よりはるか前の、子どもの頃から美容に興味を持っていました。今でも美容にまつわることが好きで、出張の際にはエステにもよく行きます。だからこそ、美容機器メーカーであるヤーマンでのキャリアを、長きに渡って心から楽しんでこられたのだと思います。
編集部|興味関心のあることだからこそ、仕事に打ち込めるのですね。
山﨑さん|社員を大切にしたいと考えたとき、まずは「仕事を好きになってもらうこと」が重要だと思うのです。人生の中で最も多くの時間を費やす仕事を、楽しんで続けられるかどうかは、幸福度に大きく影響します。私たちの会社には事務職、営業、開発、製造とさまざまな職種がありますが、仕事に共通するのは『美容と健康』という軸。ヤーマンはこの分野に特化した専業メーカーだからこそ、社員にもこのカテゴリをもっと好きになってほしい。興味を持ち、実際に体験し、仕事を通じてさらに愛着を深めていくことで、お客様の立場を理解し、より良い製品開発や販売活動につながると考えています。
自由に選べる! ヤーマンの健康・美容サポート制度

編集部がキラリを感じた「美容健康手当」
編集部|ヤーマンならではの福利厚生制度「美容健康手当」について詳しく教えていただけますか?
澤下さん|「美容健康手当」は、社員がエステティックサロンやスポーツクラブ、整体、ホットヨガなどの美容・健康に関するサービスを利用する際に、会社が費用の一部を負担する制度です。1回あたり利用額の3割、月額上限5000円までを会社が補助し、社員が好きな美容やリラクゼーション、健康増進などのサービスを選んで利用できます。
編集部|御社ならではの、ユニークな制度ですね。
澤下さん|先ほど山﨑も申し上げたとおり、ヤーマンはプロダクトの特性上、社員自身が美容や健康に関心を持つことが重要だと考えています。最新のエステなどを実際に体験することが、仕事にもつながるという考えがベースにあります。
制度誕生の裏側。「ちょっと試してみよう」と思える仕組みづくり

コロナ禍を切っ掛けに、より使いやすい制度へ
編集部|「美容健康手当」はどのような経緯で始まったのですか?
澤下さん|元々、近隣のジムを利用できる制度がありましたが、コロナ禍を機に、2022年に社員が居住地に関係なく公平に利用できる制度へと拡充しました。リモートワークの増加や全国に散らばる社員に対応するため、自宅近くのエステ、整体、サロンなどでもサービスを受けられるようにしたのです。
編集部|自分の好きな場所で、好きなサービスを受けられるのが嬉しいですね。
山﨑さん|多くの社員が「美容が好きだから」という理由で入社しますが、若い世代には、なかなか高額な美容施術には手が出ないもの。だから今こそ会社の制度を活用し、より美容に親しんでもらいたいと思います。
エステや整体、美容鍼など、どんな形でもいいので体験してみる。会社が一部負担することで「ちょっと試してみよう」と思える仕組みが、社員の成長やモチベーション向上にもつながると信じています。
他社のサービスを受けたからこそ、気づくこと

美容に関する気づきが、先進的な商品を生み出す
山﨑さん|先ほど申し上げたように、「美容健康手当」は、社員の福利厚生だけでなく、美容機器メーカーとしての事業理解を深める機会でもあります。美容の世界は幅広く多様なもの。しかしその根底には「美しくなること」に共通する喜びがあります。社員の皆さんにはご自身でさまざまな美容を実際に体験し、視野を広げて欲しいですね。
編集部|社員の方は、制度を活用することでインスピレーションを得ているのですね。
澤下さん|実際、制度を利用してエステや整体を体験することで、「この技術が自社製品に応用できるのでは」「今後流行しそうな施術や素材何か」といった新たな発見を得る社員も多いようです。また、自社製品を導入しているサロンを訪れ、お客様視点で使用感を確認できるのも大きなメリット。現場でのリアルなフィードバックが、新製品開発のヒントになることもあります。
さらに、制度を活用することで「ジムを継続するか迷っていたけれど、会社の補助があるから続けられる」といった継続の動機づけにもなり、社員の美容意識が高まる相乗効果を生んでいます。
編集部|そうした日々の気づきが、ヤーマンの先進的な商品づくりにつながっているのですね。
「向き合います」という雰囲気を醸成する環境づくり

自社のブランドを愛し、長く働くための福利厚生を
編集部| 今後はどのような福利厚生の取り組みを予定されていますか?
澤下さん| ヤーマンでは、美容に関する福利厚生だけでなく、社員のライフステージの変化にも寄り添う制度を充実させています。具体的には、産休・育休制度を通じてキャリアと子育ての両立を支援し、介護支援制度も整備することで、社員が安心して長く働き続けられる環境を提供していきたいと考えています。
編集部| ワーク・ライフ・バランスが保てることは、働くうえで大切ですね。
山﨑さん| ヤーマンの人事制度も、商品と同様に提案型にしていきたいのです。商品開発において、私たちは顧客へのヒアリングを重視しますが、その一方で本当に求められているものは、言葉にされない部分に潜んでいることが多いと考えています。だからこそ、私たちから積極的に「こんなものが欲しかったんじゃないですか?」と提案する姿勢が重要なのです。
この考え方は、人事制度にも応用できると考えています。従業員の声を聞くだけでなく、新しい働き方や福利厚生のあり方を積極的に提示していく。ライフステージとともに働き方は変化し、状況や要望も個々に異なります。そのため、職場の上司が「向き合いますよ」という雰囲気を醸成することを大切にしています。社内には「聞く準備ができているので、いつでも意見を発信してほしい」という文化を根付かせ、従業員が気軽に相談できる環境を整えています。
澤下さん| 社長自らそうした姿勢を示してくださるのは、社員にとっても大きな安心感につながっていますね。人事部としても、社員一人ひとりの声に耳を傾け、寄り添いながらサポートしていきたいと考えています。

編集部コラム
「従業員を大切にすると考えたとき、美容健康手当は“仕事を好きになり楽しく仕事をしてもらうため”の一助」と、インタビュー冒頭で語ってくれた山﨑社長。また、出産や介護、家族の転勤など年齢やライフステージによる変化に対して、寄り添うよりも向かい合い要望を聞くようにしていると語る。「社長が全社員に『聞く準備ができています。いつでも意見を発信してください』と伝えたことで文化になっている」と澤下さん。従業員の話してみようという雰囲気は、上司の姿勢が変化したことで生まれたという。人事制度はもちろんなのですが、まず相談できる風土の醸成を大切にする、キラリ企業のインタビューでした。(OZmall/NAOKO ARAKAWA)
インタビュー連載企画
~キラリ企業・ミライ人材~
編集部は考えます。“従業員を大切にしたい”企業の取り組みが“働きやすさ”につながり、その両想いの関係がミライ人材につながっていると。そこで注目の「キラリ企業」の独自の制度を深掘りし背景と想いをインタビュー!
福利厚生や社内コミュニケーションの課題解決に!
スターツ出版の法人向け新サービス「OZのギフトクーポン」
OZmall「OZのプレミアム予約サービス」を運営するスターツ出版では、法人向けギフトクーポンサービスを開始しました。法人向けサービスとしてご用意したのは、レストラン、ホテル、温泉、ビューティサロンなど編集部が厳選した施設を利用して“特別な体験”を贈ることができる『OZのギフトクーポン』。普段なかなか行くきっかけがなかったホテル宿泊や誕生日の食事、試してみたかったスパ体験などは忘れられない思い出に。会社からの労いを「記憶に残るギフト」としてお渡しできます。
企業風土の改革が必要と感じている
総務人事・経営企画ご担当様へ
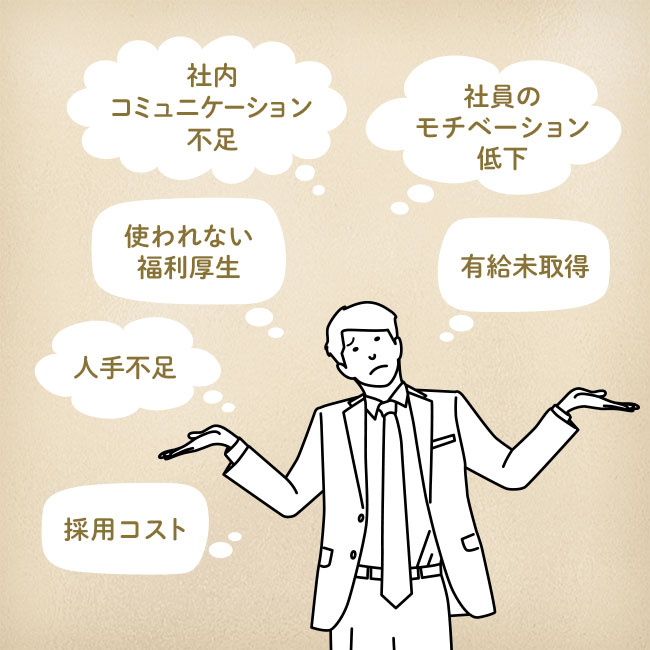
働き方改革に注目が集まるなか多くの企業での課題が「人材の強化」。有休取得奨励、社員間コミュニケーション活性など、人事・経営課題を改善へと導く一助として『OZのギフトクーポン』をご活用ください。福利厚生の強化や従業員モチベーションの向上に、従業員への“ありがとう・おめでとう”の気持ちを“記憶に残るギフト”で。
PHOTO/MANABU SANO WRITING/TOMOKO HACHIYA