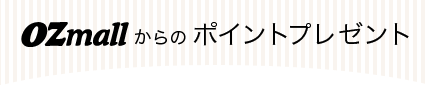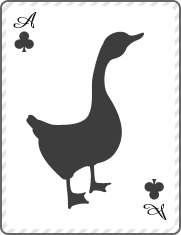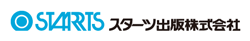家賃に食費、光熱費。ふたり暮らしにはいろんなお金がかかります。お財布の管理はどうしよう? 生活費はどう分担する? 節約はできる? ふたり暮らし経験者の女性たち500人に聞きました。
財布は分けてふたりで協力体制!

ふたりの財布は分けてる?
ここでいう「お財布」とは、すなわち「銀行口座」のこと。個別に口座を管理する「完全に別々」派(40%)のカップルが最多で、ひとつの口座にお金を「集約」する派(24%)、「共通のお財布」を作る派(22%)がほぼ同数でした。
「ふたりの収入をひとつのお財布に集約」
・一緒に住むタイミングで、彼の口座に集約しました(30歳)
・ひとつの財布にまとめたほうが支払いも貯金もしやすい気がして(34歳)
「共通のお財布にお互い一定額を入れる」
・自分の財布、相手の財布、家計の財布がある(31歳)
・口座を新たに作り、それぞれが決まった金額を振り込んでいます(27歳)
「完全に別々」
・家賃や生活費は彼が払い、同額を私が貯金している(33歳)
・品目によって、支払う人を決めています(33歳)
「その他」
・すべて彼のお金で生活しています(38歳)
・それぞれ使った分を月末に精算して折半(39歳)

よくある分担例
「完全に別々」派から多く聞こえてきたのは「品目ごとに払う人を決めている」との声。その大まかな内訳を聞いてみました。
男性は家賃などの固定費や自動で引き落とされるもの、自動車税など。女性は食品や消耗品といった日常の買い物など、現金にまつわるものを担うケースが多いようです。また、女性からは「貯蓄を担当する」といった声も多く挙がりました。
<女性>
・消耗品費
・雑費
・通信費
・保険料
・日常の買い物
・食品費、消耗品費、外食費
・レジャー
・貯蓄
<男性>
・固定費
・家賃
・食費
・自動で引き落とされるもの(光熱費など)
・医療費
・水道光熱費
・自動車税
・健康保険
・生活費全般
・住居に関する費用

口座に振り込むと「贈与」に! 誰のお金かきちんと区別して
これまで別々だった世帯がひとつになり、共同で使うものも増えるふたり暮らし。お財布はどう管理すればいいんでしょう?
「最も望ましいのは、『完全に別々にする』、あるいは『共通のお財布に、お互い毎月一定額を入れる』方式です。逆に、避けたほうがよいのは『ふたりの収入をひとつのお財布に集約』することです」と、ファイナンシャルプランナーの菱田雅生さん。というのも、パートナーの口座にお金を振り込むと、どんなに少ない金額でも贈与とみなされる可能性があるため。
「年間110万円以下の金額なら贈与税はかかりませんが、振り込んだお金は相手のものに。万一ふたり暮らしを解消する場合にトラブルになりがちです」(菱田さん)大切なのは、お金の持ち主をうやむやにしないこと。別の口座をそれぞれ持ったうえで、品目によって支払いの担当者を決める方法もよいと言います。
「また、共通のお財布として新しい口座を開設するのもよいでしょう。ただし、一般的に金融機関はふたりの名義の口座開設は受け付けていません。つまり、新しい口座を作っても、どちらかにとっては贈与になるということ。お互いに毎月の振り込み金額を決め、ルールを明記して証拠を残しておくのがスムーズな管理と言えそうですね」(菱田さん)

節約したい項目は?
日頃から支払う回数が多い「食費」(24%)を節約したいと答えた人が最多。「もともとふたりとも外食が多く、最近は彼の飲み代が増えてきた(33歳)」という声も。次いで、格安スマホの台頭によって業界全体で値下げ合戦が続く「ケータイ代」(21%)、今すぐ取りかかれそうな「光熱費」(20%)が続きました。
節約に特に効果的な3つの項目

格安スマホのサービスが充実している「ケータイ代」
まず取りかかりたいのは、毎月必ず支出することが決まっている固定費の引き下げです。固定費とはケータイ代、電話代、インターネット代、住居費、車(ガソリン、駐車場)代、保険料などのこと。月々たった1000円でも、1年間で12000円、10年間で12万円。固定費の引き下げは、長期的にも家計によい影響をもたらします。
携帯に関しては、3大キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)も値下げプランを次々と発表していますが、さらに安価なのが格安スマホ。「新たに切り換えるのは手間ですが、格安スマホに変えた途端、月々のケータイ代が半額になるケースも。現在は、キャリアで購入した本体をそのまま使える業者も登場しているので便利です。ただし、通話中心の人は割高になることがあるから注意しましょう。データ通信を中心に使う人こそ格安スマホ向き。データ通信量も少なければ少ないほど安くなります。一般的な電話に相当する3G通話のほか、LINEやSkype、Facebookメッセンジャーといった無料のインターネット通話もあるので、賢く使いたいですね」(菱田さん)

外食が多いなら、自炊に切り替えるだけで効果が大きい「食費」
食費を節約するならやっぱり自炊。ただ、共働きの場合は自炊に切り替えようとすると自分やパートナーの負担になってしまうことも・・・。
「楽しみながら切り替えるなら、こんな方法がオススメ。例えば、週4回外食しているなら週2回に減らして、あとの2回は自炊に。その代わり、週2回の外食を少しゴージャスなものにレベルアップ。回数を半分に減らし、1回の外食にかかるお金を2倍にすればこれまでの外食費と同じ。ここを1.5倍にすると、節約効果が生まれます。お互いにお弁当を作り合うのも楽しいですね。もともとは変化を嫌うのが人間。続けるためには、楽しみながら行うことがいちばんのポイントなのです」(菱田さん)

不要なものに加入しているケースが多く、見直すだけで節約になる「保険」
保険のシステムは、万一の事態に備えて多くの人がお金(保険料)を出し合い、万一の事態に遭遇した人がお金(保険金)を受け取るというもの。
「つまり、確率論上は不利になってしまうのが保険。そこで、必要最低限の保障(補償)を安い保険料で準備して、貯金を優先するという選択肢も。死亡保障は主に子供にお金を残すためのもので独身者には不要ですし、医療保障も都民共済や県民共済、あるいはネット系の保険会社の医療保障にひとつ入っておけば十分。これらは比較的安価に加入できます。また、ライフステージや生活の状況は絶えず変化するため、1年に一度くらいの頻度で保険を見直すのがベストです」(菱田さん)
節約は固定費の引き下げから!アプリで使途不明金を減らそう
「アンケートで5人に1人が節約したいと回答した『光熱費』(20%)は、チリツモではあるものの、がんばっても劇的な節約は望めません。『家賃』(14%)や『被服費』(8%)も無理にレベルを下げると生活がつらくなってしまいます」と菱田さん。その点、大きな節約効果があって、生活を切り詰める苦しさを感じにくいのが「ケータイ代」(21%)と「保険料」(7%)の見直しです。
同時に、節約を始める際にはぜひ試してほしいのが家計簿を付けることなんだとか。
「アナログの時代は面倒でしたが、今は便利なアプリが多数出ています。現状の家計を把握することでムダの多い支出項目が見えやすくなり、支出への意識が強くなると自然と使途不明金も減りますよ」(菱田さん)
たとえば「Zaim」「マネーフォワード」といったアプリは支出項目が細かく分類され、レシートをカメラで写すだけで自動的に金額を読み込む機能や銀行口座やクレジットカードとの連携機能、互いの支出が見える共有機能が付いているなど、至れり尽くせり。
「ふたり暮らしは共同で使うものが増えるため節約にぴったり。さらに共働きなら二馬力で稼げるので、お金をぐんぐん貯める絶好のチャンスでもあるんですよ!」(菱田さん)
話を聞いた人
菱田雅生さん
1969年生まれ。資産運用や住宅ローンなどを中心としたアドバイスを行うライフアセットコンサルティング代表。相談業務や原稿執筆、セミナー講師などに従事するかたわら、テレビ・ラジオ出演などもこなす。『超・資産形成入門』『お金を貯めていくときに大切なことがズバリわかる本』など著書多数

本に教えてもらうなら
『経済ってそういうことだったのか会議』
- 著者
- 佐藤雅彦、竹中平蔵
- 発行
- 日経ビジネス人文庫
- おすすめポイント
- わかりやすさ重視のやさしい経済入門書。ふたりのうちどちらかが読んで、相手に教えてあげれば、コミュニケーションツールにもなります
- あらすじ
- この地球上で展開される経済について、メディアクリエイターの佐藤雅彦と経済学者の竹中平蔵が、独自の目線からわかりやすく解説。経済に苦手意識のある人にこそオススメしたい、トリビアたっぷりのビギナーズガイド
【特集】本が教えてくれる、はじめてのふたり暮らし

はじめてのことをするとき、本は道しるべになってくれます。具体的な対応策や、思いも付かないようなアイデア、気付きや考え方のヒントを与えてくれたり。それは「ふたり暮らし」もきっと同じ。みなさんの暮らしのお悩みや疑問を、本を軸に解決策をご提案する特集です。
TEXT/AYAHA YAGUCHI