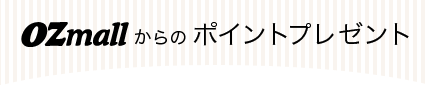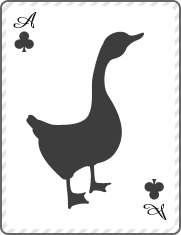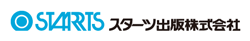リモートワーク不眠は“朝の窓際時間”で解消を
不眠と深く関係するのが、睡眠を促すホルモンであるメラトニン。人間は起床後、目に光が入るとメラトニンの分泌量が減って心身が覚醒し、その16時間後にメラトニンの分泌量が増えて眠気が生まれるしくみになっている。このとき、起床後の光が強いほどメラトニンの分泌量が大きく減ってすっきりと目が覚め、その16時間後にぐっと分泌量が増えて深い眠りを促すのだそう。
ところが、リモートワークで自宅から一歩も外に出ないまま仕事をはじめると、朝の起床後に受ける光が弱く、メラトニンがあまり減らないまま日中を過ごすことになるため、昼間も眠気が残ってしまう。しかもこの場合、起床16時間後になってもメラトニンの分泌量があまり増えず、夜はなかなか眠気が訪れない。結果、昼間はずっと眠く、夜になると目がさえるという状態に。
「コロナ禍以前は、出勤時に自然と太陽の光を浴びることができましたが、リモートワークが普及してからはこうした症状が増えてきました。特に、もともと週末に寝だめをする傾向がある人や、月曜日がつらく感じる人、平日と週末では起床時間が大きく違う人はリモートワークの影響で不眠になりやすいといえます」(菅原さん)
こうした不眠が気になる人は、朝起きたらまずは窓際に移動して、楽しい時間を過ごすことを習慣にしてみて。寝起きのスマホチェックやコーヒータイム、朝食を取る場所などを窓際にするだけで、毎朝自然と太陽の強い光を浴びる生活を送れるようになり、不眠の改善につながるはず。

ベッドでの過ごし方が“眠りやすい脳”を作る
また、ベッドでの過ごし方を見直すこともリモートワーク不眠の対策になるのだと、菅原さん。まず、ベッドの上では寝ること以外の行動をしないことが大切なポイント。
「ベッドの上でスマホを見たり本を読んだりすると、脳は『ベッドはスマホを見たり本を読んだりする場所』と学習してしまいます。すると、ベッドに入ると脳が自動的にスマホや本から情報を得ようとするモードになり、眠気が訪れにくくなるのです」(菅原さん)
必ずしも夜のスマホや読書をがまんする必要はないけれど、ベッド以外の場所で行うことが重要。ベッドに入ったら寝るだけ、という行動を習慣にすることで「ベッドは寝る場所である」と脳が学習しなおすことができ、眠りにつきやすくなる。
そしてもうひとつ、眠くなるまでベッドに入らないことも意識してみて。眠くないうちからベッドに入ると、ベッドで考えごとをしてしまうため、脳が「ベッドは考えごとをする場所」と学習して次第に眠つきが悪くなってしまう。
「脳科学的には、眠くなるまでベッドに入らないことが適切ですが、これはあくまで基本原則です。いくら眠くなくても夜遅くまでベッドに入らないのは不安という場合は、がまんせずにベッドに入りましょう」(菅原さん)

起床11時間後の運動も深い眠気を誘うポイント
夜の深い眠りを作るためには、深部体温に着目することも効果的。深部体温とは内臓の温度のことで、起床して11時間後に最も高い温度になる。このピーク時の深部体温が高いほど夜の眠気が強くなるので、その温度を高めるために体を動かすことがおすすめ。
「例えば朝7時に起床したなら、11時間後の18時に体を動かすことでピーク時の深部体温を高めることができます。体を動かすといっても特別な運動ではなく、部屋の掃除をする、買いものに出かけるなど、体を動かす用事をこの時間帯にこなすという考え方で十分です。これを週4回以上実践できれば、夜に眠気が生まれやすくなるでしょう」(菅原さん)
睡眠リズムの乱れに漠然とした不安を感じている人は、睡眠の記録をつけてみて。大学ノートの罫線に24時間のメモリを入れ、寝ている時間を黒く塗り、眠るまでのベッドに入っていた時間は矢印を引くだけ。黒い部分と白い部分が細切れに混ざり合っている場合は、寝たり起きたりを繰り返していて睡眠リズムが乱れている状態。矢印の長さが30分以上になる場合は、寝つきが悪い状態。一方、黒い部分が夜に5時間以上連続している時間帯があれば、睡眠リズムが良好な状態なのだそう。
「睡眠の記録をつけるとひと目で睡眠状態が把握でき、睡眠リズムが乱れるときのパターンが見つかったり、寝つきが悪いならベッドに入る時間を変えたりするなど、改善策も見つけやすくなります。睡眠状態が“見える化”されることで、不安感もやわらぐでしょう」
リモートワーク不眠は、こうした対策でかなり解消が期待できるとか。質のいい睡眠を得るためのいい機会と捉えて、生活習慣を見直してみて。
教えてくれた人
菅原洋平さん
作業療法士。ユークロニア株式会社代表。アクティブスリープ指導士養成講座主宰。国際医療福祉大学卒。国立病院機構にて脳のリハビリテーションに従事したのち、現在は、ベスリクリニック(東京都千代田区)で薬に頼らない睡眠外来を担当するかたわら、生体リズムや脳の仕組みを活用した企業研修を全国で行う。13万部を超えるベストセラー『あなたの人生を変える睡眠の法則』(自由国民社)、12万部突破の『すぐやる!「行動力」を高める科学的な方法』(文響社)、『働く人の疲れをリセットする 快眠アイデア大全』(翔泳社)など著書多数。
【特集】プチ不調や身体の悩みを解消!すこやかなココロとカラダへ

毎日がんばる働く女性にプチ不調や悩みはつきもの。そこでみんなが気になる健康法やグッズ、食材やドリンク、悩みの解決法やメカニズム、取り入れたい習慣などを専門家やプロのお話しとともにご紹介。自分のココロとカラダに向き合って、健やかに私らしく。オズモールはそんな“働く女性の保健室”のような存在をめざします
こちらもおすすめ。ヘルスケアNEWS&TOPICS
WRITING/TOMOKO OTSUBO